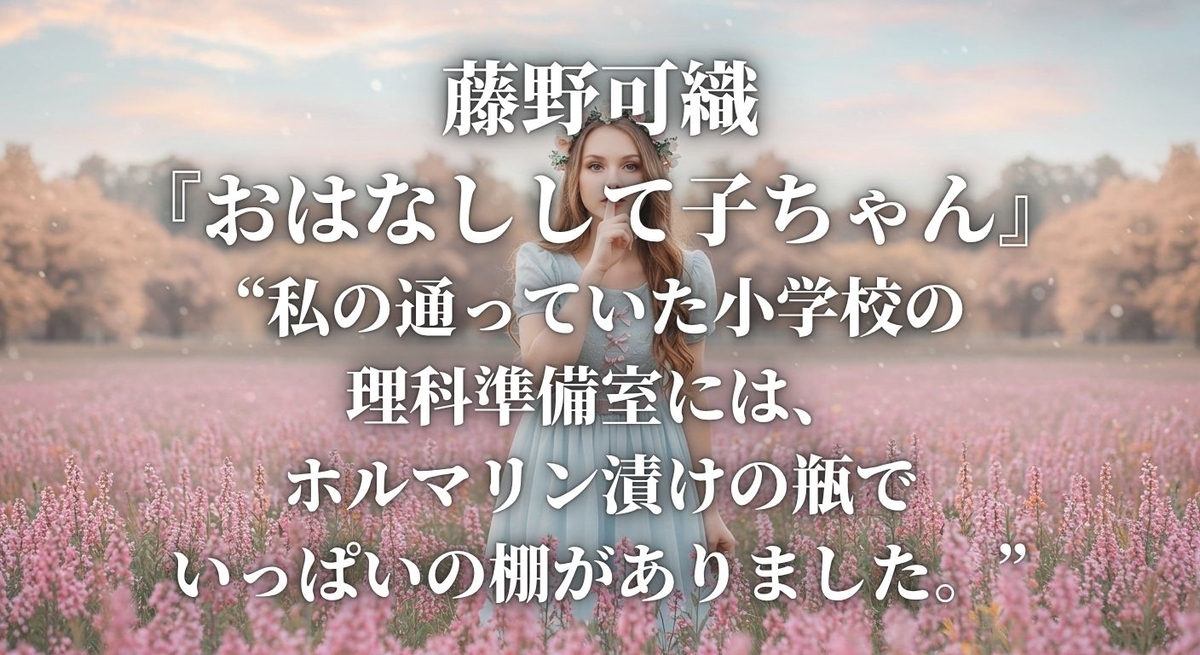
藤野可織さんの短篇集『おはなしして子ちゃん』を読み終えました。以前読んだ『ドレス』を読んで興味を持った作家さんです。『おはなしして子ちゃん』もその世界観に一気に引き込まれてしまいました。この短篇集には、私たちの日常のすぐそばに潜む、少しだけ歪んだ、あるいはゾッとするような出来事が詰まっています。読んでいると、まるで現実と非現実の境界線が曖昧になっていくような不思議な感覚になります。
藤野可織『おはなしして子ちゃん』
あらすじ
ピエタのクラスに黒髪の転校生トランジがやって来た。「私の近くにいるとみんなろくな目に遭わない」というトランジの言葉を裏付けるように、学校で次々に殺人や事故が起きて……!?(「ピエタとトランジ」)
猿と鮭の死骸をくっつけて人魚を作る工場で、なぜか助六が作る商品には人魚としての自覚が足りない。人魚になりきれぬまま、「それ」は船に積まれ異国へと旅立ったが――(「アイデンティティ」)
14歳の夏、高熱を出した少女エイプリルは、後遺症で一日に一回嘘をつかなければ死んでしまう体になってしまった。美人のエイプリルを守るため、町の人々は様々な犠牲を払うが……(「エイプリル・フール」)
ブラックで残酷、不気味で怖いけれど、ファンタジックでキュートな10篇の作品たち。新しい才能が迸るポップ&ダークな短篇集です。
作品の魅力・ポイント・感想

『おはなしして子ちゃん』
表題作の「おはなしして子ちゃん」は、小学生の頃の理科準備室にまつわる物語です。ホルマリン漬けの猿の標本を巡る子供たちのやり取りが描かれるのですが、その中に子供ならではの無邪気さと、時に残酷な一面が見え隠れします。特に印象的なのは、ある嘘がきっかけで、物語が思わぬ方向へ転がっていくところです。理科準備室という閉鎖的な空間と、そこにいる不気味な存在、そして子供たちの心理が巧みに描かれていて、読んでいるとじわじわと恐怖が忍び寄ってくるのを感じました。日常の中にある、ほんの少しの悪意や好奇心が、取り返しのつかない事態を引き起こす可能性を示唆しているようで、読後も心に残る一編でした。
『ピエタとトランジ』
「ピエタとトランジ」は、都会を舞台にしたミステリアスな雰囲気の作品です。大学生のピエタと、転校してきた掴みどころのない少女トランジの関係性が中心に描かれます。物語は、ある衝撃的な出来事をきっかけに大きく動き出すのですが、そこで見せるトランジの冷静さや、少し歪んだ言動が強く印象に残ります。彼女の過去に触れる部分では、そのキャラクターの背景にあるものが垣間見え、さらに物語に深みが増します。単なる事件の真相を追うだけでなく、登場人物たちの内面や、人間関係の奇妙さが描かれていて、都会の片隅に潜む孤独や、人との繋がりの危うさを感じさせる作品でした。
『アイデンティティ』
「アイデンティティ」は、「人魚工場」というユニークな設定が目を引く作品です。ここでは文字通り「人魚」が作られているのですが、その製造過程が非常に生々しく描かれています。私たちが抱く人魚のイメージとはかけ離れた、ある意味で残酷な描写を通して、存在しないものを作り出す人間の営みや、そこに潜む欲望が浮き彫りになります。「存在しないからこそ価値がある」という逆説的な視点が提示されていて、現代社会における価値観や、実体のないものに人々が惹きつけられる様子を風刺しているようにも読めます。ファンタジーでありながら、人間の業のようなものを感じさせる、示唆に富む作品でした。
『今日の心霊』
「今日の心霊」は、生まれつき心霊写真が撮れてしまう少女micapon17の人生を追った、ドキュメンタリーのようなタッチの作品です。彼女自身には心霊が見えないという設定が面白く、その純粋さと、周囲の反応とのギャップが印象的です。才能を持ってしまったがゆえに巻き起こる騒動や、インターネット上での出来事など、現代的な要素も盛り込まれています。異質な才能を持つ個人が、社会の中でどのように扱われていくのかが描かれていて、考えさせられる部分が多くありました。ブラックユーモアと、どこか哀愁漂う雰囲気が心地よく、micapon17というキャラクターがとても魅力的で、この短篇集の中でも特に好きな作品の一つです。
『美人は気合い』
「美人は気合い」は、語り手の正体が次々と変化していく、読者の予想を裏切る構成が特徴的な作品です。最初は人間ではないような存在の視点から始まるのですが、読み進めるうちに意外な事実が明らかになり、物語の世界観が一変します。人類の存続に関わる壮大なテーマが語られる一方で、導入部分の奇妙な語り口との対比が印象に残ります。予測不能な展開と、スケールの大きなテーマが組み合わさることで、短いながらも読者に強いインパクトを与える作品でした。
『エイプリル・フール』
「エイプリル・フール」は、「一日に一回必ず嘘をつかなければならない」という、シンプルながらも強烈な設定を持つ作品です。嘘をつかないと死んでしまうという運命を背負った少女の物語なのですが、この不条理な設定が様々な解釈を可能にしています。文字通りの物語として読むこともできますし、現代社会における「嘘」のあり方や、思春期の少女が抱える生きづらさを象徴していると捉えることもできます。奇妙な設定の中に、人間の本質や社会の歪みが垣間見えるような、藤野可織さんらしい「狂気」が感じられる一編でした。
『逃げろ!』
「逃げろ!」は、「頭のおかしい人間」を自称する通り魔の視点から描かれる、非常に衝撃的な作品です。彼の独特な論理や、奇妙な凶器へのこだわりが強く印象に残ります。暴力的な描写も含まれていますが、語り口にはどこか飄々とした、あるいは哲学的な雰囲気が漂っていて、そのギャップが独特の不気味さを生み出しています。物語の後半で明らかになる、彼を追う人物との関係性もまた「狂気」を感じさせます。人間の心の奥底にある闇や、理解不能な行動が描かれていて、読んでいるとゾッとさせられる一方で、藤野可織さんの筆致に引き込まれる作品でした。
『ホームパーティーはこれから』
「ホームパーティーはこれから」は、この短篇集の中では比較的穏やかな雰囲気の作品かもしれません。「今日は私の人生の、新しい段階にさしかかる日だ。私はちょっと緊張している。」という書き出しからは、主人公にとって何か重要な出来事が始まる予感が伝わってきます。他の作品のような強烈な「狂気」や不条理さとは異なるかもしれませんが、日常の中のささやかな心の動きや、これから起こるであろう出来事への期待感や不安を描いているのかもしれません。
『ハイパーリアリズム点描画派の挑戦』
「ハイパーリアリズム点描画派の挑戦」は、芸術への異常なまでの情熱と、それを取り巻く現代社会の様相を描いた、風刺的な要素を含む作品です。数年から十年かけて点描を描き続ける画家たちの姿や、彼らの作品が展示される展覧会の様子が描かれるのですが、そこで起こる出来事が非常に衝撃的です。美術鑑賞という行為の常識を覆すような描写を通して、芸術が持つ力や、それに駆り立てられる人間の情熱、そして大衆の熱狂の異様さが浮き彫りになります。芸術と暴力という異質な要素を組み合わせた、藤野可織さんらしい作品でした。
『ある遅読症患者の手記』
「ある遅読症患者の手記」は、「遅読症」というユニークな設定を通して、「読む」という行為そのものに深く切り込んだ作品です。文字を読むのが極端に遅い主人公の視点から、読むことの困難さや、文字という存在に対する彼の独特な向き合い方が描かれます。特に印象的なのは、読むという行為を、地面にうずくまり蟻をつぶすような行為に例える描写です。そして、物語の最後のページが「本の血」で真っ赤になるという結末は、非常に象徴的で強烈なイメージを残します。読むという日常的な行為に潜む異様さや、文字の持つ力を改めて考えさせられる、示唆に富む一編でした。
おわりに

藤野可織さんの短篇集『おはなしして子ちゃん』は、日常のすぐ隣に潜む「狂気」と、それを時にブラックユーモアを交えながら描き出す藤野可織さんの手腕が光る一冊でした。一篇一篇が非常に個性的で、読者の心に強い印象を残します。予測不能な展開と、人間の心の闇を覗き込むような描写は、読んでいる間ずっとゾクゾクさせられました。単なるホラーや不気味さに留まらず、どこかユーモラスで哀愁も感じさせる独特のトーンが、藤野可織さんの作品の大きな魅力だと思います。刺激的な読書体験を求めている方や、日常の「普通」に少し飽きてしまった方に、ぜひ手に取っていただきたい短篇集です。藤野可織さんの他の作品も、これからぜひ読んでみたいと思っています。
