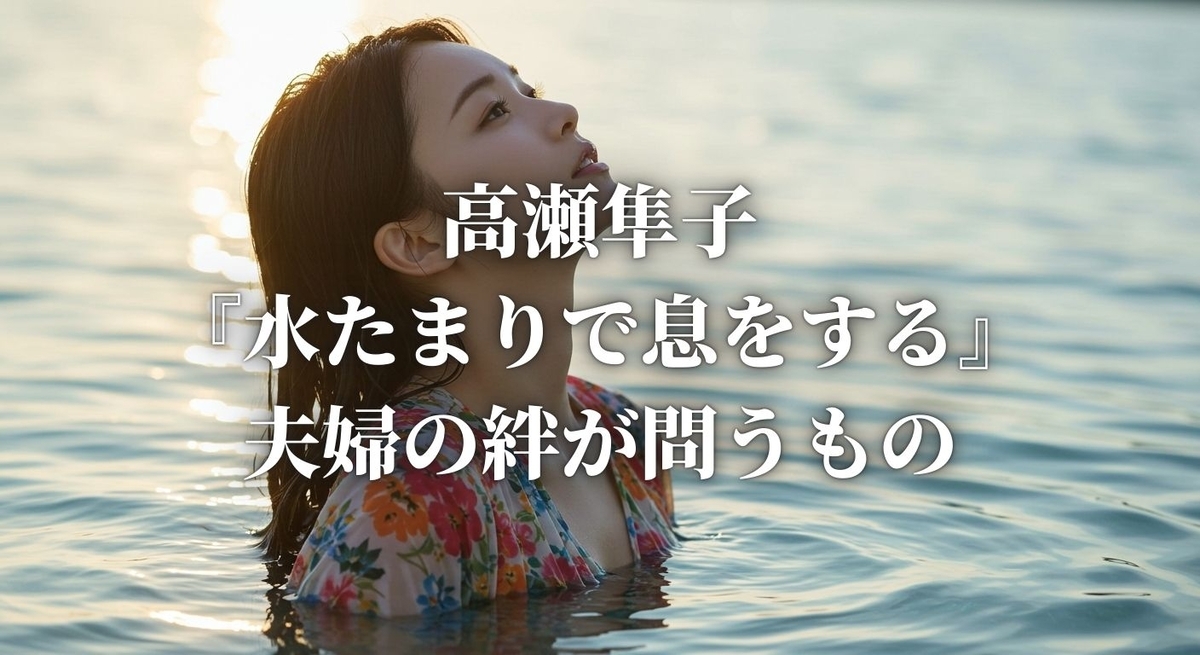
高瀬隼子さんの『水たまりで息をする』は、現代社会の中で生きる人々の苦悩と葛藤を鮮烈に描き出した衝撃作です。突如として風呂に入れなくなった夫と、その夫を支える妻の物語を通じて、私たちが当たり前だと思っている「普通」の生活がいかに脆いものであるかを浮き彫りにしています。
高瀬隼子『水たまりで息をする』
あらすじ
ある日、夫が風呂に入らなくなったことに気づいた衣津実(いつみ)。夫は水が臭くて体につくと痒くなると言い、入浴を拒み続ける。彼女はペットボトルの水で体をすすぐように命じるが、そのうち夫は雨が降ると外に出て濡れて帰ってくるように。そんなとき、夫の体臭が職場で話題になっていると義母から聞かされ、「夫婦の問題」だと責められる。夫は退職し、これを機に二人は、夫がこのところ川を求めて足繁く通っていた彼女の郷里に移住する。そして川で水浴びをするのが夫の日課となった。豪雨の日、河川増水の警報を聞いた衣津実は、夫の姿を探すが……。女性が主体として生きていくことの難しさを描いた物語。
作品の魅力・ポイント

不条理な状況に直面する夫婦の姿
物語の中心にあるのは、ある日突然、水道水を嫌がり風呂に入れなくなった夫と、その状況に戸惑いながらも夫を支えようとする妻・衣津美です。高瀬さんは、この不条理な状況を通じて、私たちが普段気づかない社会の歪みや、人間関係の複雑さを巧みに描き出しています。
「普通」という概念への問いかけ
この小説の大きな魅力の一つは、「普通」とは何かという問いを読者に投げかけている点です。夫の行動は一般的な基準からすれば「普通」ではありませんが、そもそも「普通」の基準とは何なのでしょうか。高瀬さんは、この問いを通じて私たちの価値観や社会の規範に疑問を投げかけています。
現代社会の生きづらさを映し出す鏡
本作は、現代社会で生きることの難しさを鋭く描き出しています。水道水を嫌がる夫の姿は、ある意味で現代社会のストレスや不安を象徴しているとも言えるでしょう。高瀬さんは、この物語を通じて、私たちが日々直面している見えない圧力や、それに対する人間の脆さを浮き彫りにしています。
感想

『水たまりで息をする』を読んで、まず感じたのは息苦しさと同時に、どこか自分にも起こりうる出来事のような不思議な親近感でした。高瀬さんの作品には、いつも読者を不安にさせる力があります。
物語の中で、夫が水道水を「臭い」と感じ始めるシーンは特に印象的でした。誰もが経験したことのある「何かがおかしい」という感覚を、高瀬さんは見事に言語化しています。そして、その感覚が少しずつ膨らんでいき、最終的に日常生活を脅かすまでになる過程が、とてもリアルに描かれています。
この作品の中で、私が最も心を打たれたのは妻・衣津美の姿です。夫の異変に戸惑いながらも、彼女は夫を見捨てることなく、むしろ一緒に新しい生活を模索しようとします。この選択に、私は深い愛情を感じました。現代社会では、問題から逃げることも一つの選択肢として認められつつありますが、衣津美の行動は、そうした風潮に一石を投じているようにも感じられます。
同時に、この物語は現代社会の生きづらさを如実に表現しています。「普通」であることの難しさ、そして「普通」から外れてしまったときの孤独感。これらは、多くの読者の心に響くテーマだと思います。
おわりに

『水たまりで息をする』は、現代社会の闇と光を鮮やかに描き出した作品です。
この作品の最大の魅力は、「普通」という概念に疑問を投げかけ、私たちの価値観を揺さぶる力にあります。同時に、困難な状況下でも互いを支え合おうとする夫婦の姿を通じて、人間の強さと弱さを描き出しています。
