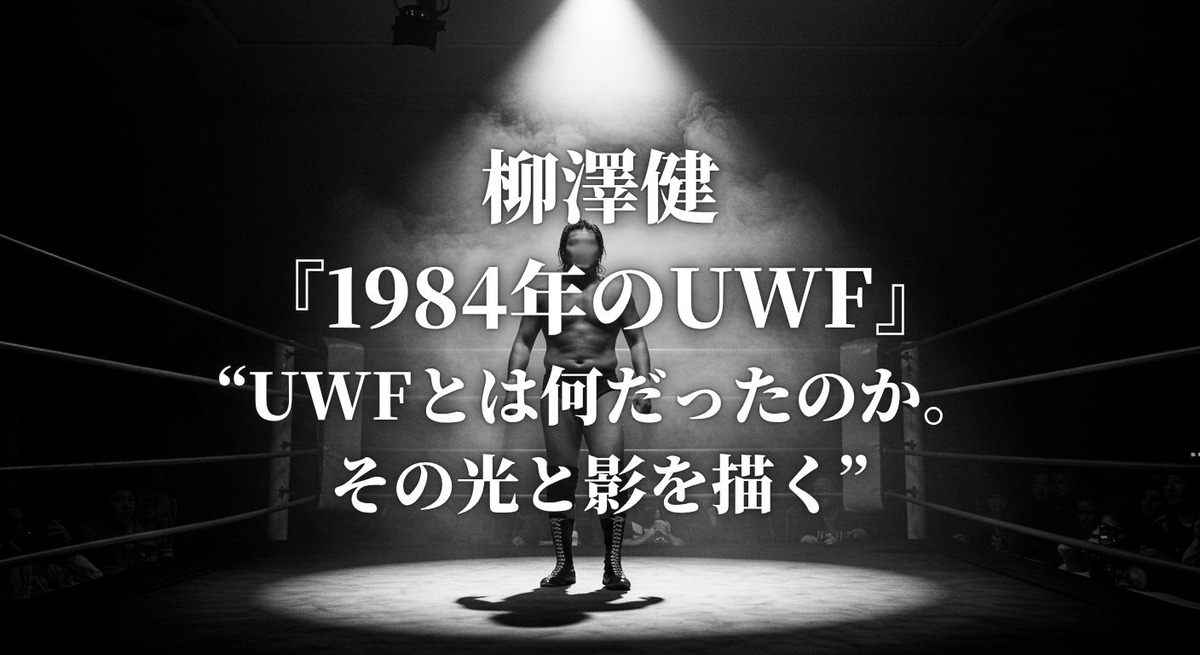
1984年、日本のプロレス界は大きな地殻変動に見舞われました。アントニオ猪木率いる新日本プロレス、ジャイアント馬場が築いた全日本プロレスという二大巨頭が君臨していた時代に、敢然と反旗を翻した団体がありました。その名は「UWF」。彼らが掲げたスローガンは、あまりにもシンプルかつ過激でした。それは「真剣勝負」という、当時のプロレス界の常識を根底から覆す挑戦状だったのです。
柳澤健さんのノンフィクション本『1984年のUWF』は、この伝説のプロレス団体が生まれ、燃え上がり、そしてその後の格闘技界に計り知れない影響を与えていくまでの軌跡を、克明に、そして時に冷徹な視点で描き出した傑作です。本書は単なる懐古趣味の記録ではありません。それは、理想と現実、情熱とビジネス、そして「強さ」とは何かという根源的な問いに満ちた、男たちの壮大なドラマなのです。
この記事では、UWFがプロレス界に巻き起こした革命の舞台裏と、そこに生きた男たちの情熱、そして私自身が本書を読んで感じた衝撃について語っていきたいと思います。
柳澤健『1984年のUWF』
内容紹介
プロレスか? 格闘技か?
現在のプロレスや格闘技にまで多大な影響を及ぼしているUWF。新日本プロレスのクーデターをきっかけに、復讐に燃えたアントニオ猪木のマネージャー新間寿が1984年に立ち上げた団体だ。アントニオ猪木、タイガー・マスクこと佐山聡--、新間にとって遺恨はあるが新団体UWFにはふたりの役者がどうしても必要だった。UWF旗揚げに関わる男達の生き様を追うノンフィクション。佐山聡、藤原喜明、前田日明、髙田延彦……、彼らは何を夢見て、何を目指したのか。果たしてUWFとは何だったのか。この作品にタブーはない。筆者の「覚悟」がこの作品を間違いなく骨太なものにしている。
作品の魅力・ポイント・感想

プロレス革命の舞台裏ー「真剣勝負」という名の熱狂
本書を読み解く上でまず理解すべきは、UWFが誕生した当時のプロレス界の空気です。それは、ショーとしての側面が色濃く、ストーリーラインやアングルがファンを楽しませる、いわば「予定調和」の世界でした。しかし、ファンの心の奥底には、常に一つの渇望がありました。「本当に強いのは誰なのか?」という、純粋な問いです。
UWFは、その渇望に応えるかのように現れました。新日本プロレスを離脱した選手たちが中心となり、キックやサブミッション(関節技)を主体とした、格闘技色の濃いスタイルをリングに持ち込んだのです。派手な必殺技の応酬ではなく、一瞬の隙を突いた関節技で勝負が決まる。その緊張感とリアリティは、これまでのプロレスに物足りなさを感じていたファンを瞬く間に虜にしました。
しかし、本書が暴き出すのは、その熱狂の裏に隠されたもう一つの真実です。柳澤さんは、当時の関係者への丹念な取材を通して、「真剣勝負」というスローガンの裏側で、それが興行として成立するための様々な葛藤や計算があったことを明らかにします。ファンが「ガチンコだ」と信じて熱狂した試合も、実は選手同士の深い信頼関係と暗黙の了解の上に成り立っていた「プロレス」であったこと。ブームの最中でも、経営的には常に綱渡りの状態であったこと。本書は、私たちが抱いていたUWFという「幻想」に、鋭いメスを入れていきます。この「幻想」と「現実」のギャップこそが、UWFという現象を読み解く鍵となるのです。
登場人物たちの情熱と葛藤ー強さを求めた男たち
UWFの物語をこれほどまでに魅力的にしているのは、そこに集った選手たちの、あまりにも人間臭い情熱と葛藤です。本書は、特に二人の天才を中心に、そのドラマを鮮やかに描き出します。
一人は、初代タイガーマスクとして一世を風靡した佐山聡。彼は、単なるプロレスラーではなく、武道家であり、真理の探求者でした。本書で描かれるタイガージムでの指導は、常軌を逸した厳しさで知られていますが、それは単なるしごきではありませんでした。彼の中には「シューティング(のちの修斗)」という、打・投・極を融合させた新しい格闘技のビジョンが明確にあり、その理想を実現するための、一切の妥協を許さない訓練だったのです。佐山は、プロレスという枠組みの中にいながら、常にその向こう側にある「真の強さ」を見据えていました。彼の孤高の精神と、時代がまだ彼に追いついていなかったという悲劇性が、本書からはひしひしと伝わってきます。
そしてもう一人が、佐山聡脱退後のUWFを牽引した前田日明です。彼もまた、「強さ」への渇望を抱き続けた男でした。前田の持つカリスマ性と、相手の攻撃を真正面から受け止めるファイトスタイルは、ファンの心を鷲掴みにしました。しかし、彼もまた、理想とする格闘技と、興行としてのプロレスとの間で常に揺れ動きます。団体を背負うエースとしての責任、他の選手たちとの軋轢、そして自らが信じる「UWFイズム」とは何かという問い。その苦悩と葛藤が、前田日明というレスラーを、より一層魅力的な存在にしていたのです。
本書は、この二人だけでなく、高田延彦、山崎一夫といった、UWFを支えた他の選手たちの姿も丁寧に追いかけます。彼ら一人ひとりが抱いていた思いが交錯し、ぶつかり合うことで、UWFという奇跡の熱狂が生まれたことがよくわかります。
私が感じた「UWFもプロレスだった」という衝撃
正直に告白すると、私はUWFについて、ほとんど知識がありませんでした。私がプロレスに夢中になったのは1990年代の後半、すでにUWFは解散し、その遺伝子を受け継いだ団体が乱立していた時代です。そのため、UWFは「伝説」ではあっても、リアルタイムの熱狂としては知りませんでした。名前を知っている程度の、いわば「にわかプロレス好き」だったのです。
だからこそ、本書を読んで最も衝撃を受けたのは、「UWFもまた、プロレスだった」という、身も蓋もない事実でした。
私が漠然と抱いていたイメージは、「UWF=ガチンコ格闘技」というものでした。しかし、本書が描き出すのは、それがいかに単純な見方であったかということです。「真剣勝負」を謳いながらも、そこには観客を魅了するためのショーマンシップがあり、選手同士の信頼関係に裏打ちされた攻防がありました。それは、私が知っている「プロレス」そのものだったのです。
この発見は、Amazon Prime Videoの人気番組『有田と週刊プロレスと』でプロレスの歴史を学んでいた私にとって、まさに目から鱗が落ちる体験でした。番組で語られる様々な団体の歴史や選手たちのエピソードが、本書の内容と結びつき、一つの壮大な物語として立ち上がってきたのです。「あの事件の裏には、こんな人間ドラマがあったのか」「この選手の行動は、UWFの思想が原点にあったのか」と、知識が繋がる快感は、何物にも代えがたいものでした。
UWFの試合は、決して八百長ではありません。しかし、完全なノールールの殺し合いでもない。その絶妙なバランスの上に成り立っていたからこそ、ファンはそこに「本物」のドラマを感じ、熱狂したのです。本書は、そのプロレスというジャンルが持つ、一筋縄ではいかない奥深さと面白さを、改めて私に教えてくれました。
おわりに

柳澤健さんの『1984年のUWF』は、単なるプロレスの歴史を綴った一冊ではありません。
それは、一つの時代を全力で駆け抜けた男たちの、情熱と葛藤、そして夢と挫折の物語です。彼らがリングの上で体現しようとした「真剣勝負」という理想は、決して消えることなく、形を変えながら現在の総合格闘技へと確かに受け継がれています。UWFなくして、日本の格闘技の今はなかったと言っても過言ではないでしょう。
プロレスファンはもちろんのこと、格闘技が好きな方、そして何かに熱中した経験のあるすべての人に、この本を強くおすすめします。読み終えた時、きっとあなたの心にも、あの時代のリングサイドに吹いていた熱い風が感じられるはずです。

